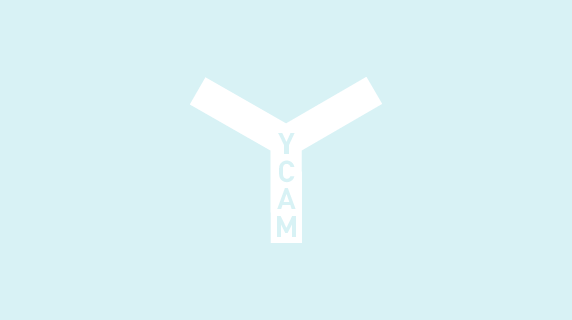わたしとYCAM
仕事から遊びへの緩やかな移行
「爆音上映のホームはYCAM」と言い始めたのは2015年ごろ、つまりYCAMでの爆音映画祭を開始して3年目くらいからのことだったと思う。機材やスタッフの素晴らしさや豊富さはもちろん、うれしかったのは上映にまったく関係のないスタッフたちも上映を見てくれて、そして今度はあれが観たい、これが観たいとまるで学園祭のように楽しんでくれたことだ。
吉祥寺バウスシアターで爆音上映を立て続けにやっていたころも、そんな感じだった。劇場スタッフやアルバイトたちと集い語り合いながら次の企画が決まり、みんな喜んでその準備に入っていった。仕事のはずがいつの間にか遊びになり、その境目が消えたまま10年間が過ぎた。もちろんそれぞれがプロとしての仕事をやったうえでのことだ。そのうえでさらに無茶な要望や無茶な企画を持ち込んで遊ぶ。もちろんすべてがうまくいっていたわけではない。だがそれでいいのだ。そんな空気の中で爆音映画祭は育っていった。そんなバウスと同じ空気がYCAMにも流れている。その感触が「ホーム」発言となったわけである。
おかげでまるで1年に1度実家に帰って自分のやってきたことを見つめ直すように、YCAM爆音映画祭をやらせてもらった。爆音映画祭の再生と実験の場所として。そして何よりもリラックスして楽しみながら。最初、通常の映画館と同じ5.1チャンネルとして配置されていたスピーカーは何年かのうちに天井にも座席下にも配置され、そして壁際に配置されたサラウンド用のスピーカーはメインのスピーカーとしても使えるような高性能ハイパワーのスピーカーとなっている。そんな爆音上映のための贅沢且つ実験的な試み、つまり大人の遊びによって、映画の音は思わぬ変化を見せる。
2015年の『未知との遭遇』ではまさに会場の上からUFOが降下した、としか言えないような体感を得た。2016年の『インターステラー』では一瞬の無音部分で呆然とした。そして2019年は決して大きな音があるわけではない『寝ても覚めても』や『ファントムスレッド』をとりあげて、主人公たちの息遣いや状況による音の変化によって目が耳となり耳が目となるような、視覚と聴覚とのかつてない混乱と融合を体感した。
それらはYCAMという場所の作り出したものだと思う。現実には音響システムと音の調整によって生まれた音だが、しかしこればかりはYCAMなしではありえなかった。仕事から遊びへという緩やかな移行の中で何かが生まれる。そこでは作り手だけではなくそこにやってくる「観客」もまた、何かを生み出すことになる。音を聞くことが新たな作品や企画を生み出し、作り手から受け手へという流れを循環させるのだ。口先だけの「参加型」とはまったく違うだれもが参加できる運動を、YCAMは作り出しているように思う。